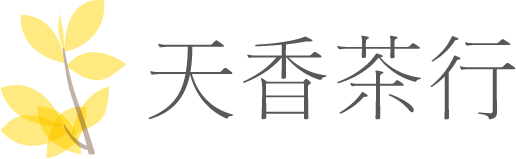豆知識 1 蓋碗

蓋碗と茶壺
中国でも日本と同じように茶葉にお湯を注いで飲む「泡茶」というスタイルが主流ですが、さらに泡茶には日本の急須にあたる茶壺を使う飲み方と、蓋碗を使う飲み方があります。蓋碗をもらったが飲み方がわからず、茶葉が口に入っていたといった誤解もあるようですので、ここでご簡単に茶器の使い方をご説明いたします。
また、天香茶行で蓋碗をお買い上げいただいた場合には同様の説明書を同封いたしますので、ご安心ください。
また、天香茶行で蓋碗をお買い上げいただいた場合には同様の説明書を同封いたしますので、ご安心ください。
蓋碗の使い方

青花磁(糸瓜)
泡茶というのは茶にお湯を注いで浸みだした茶水を飲むという、今の私たちにとっては当たり前の飲み方ですが、宋の時代、日本で言えば平清盛くらいの時代には茶葉を粉にしてこの粉ごと飲んでいました。これが日本に伝わり抹茶として残っていますので、想像しやすいと思います。蓋碗を使った飲み方はこの延長にありますが、葉は飲まず茶水だけを啜ります。中国茶の茶葉は大きいので茶漉しを使わなくても蓋碗という茶器があれば十分なのです。
●蓋碗のコップ使い
蓋碗は「碗蓋(フタ)」「碗身(本体)」「碗托(皿)」の3つのパーツでできています。茶芸のような詳細な手順は省き、蓋碗を1人1個使う基本的な飲み方をご説明します。この飲み方は実にカンタンで意外に合理的。昔から緑茶を飲む際のメジャーな飲み方です。
1.湯で碗身をあたためる。
お茶の種類によりますが、湯の温度が低いと成分が出にくくなります。まずは湯を入れて碗身を温めた後、湯を切っておきましょう。
2.茶葉を入れる
3.湯を注ぐ
烏龍茶は沸騰したお湯、高級な緑茶などは色香味が落ちますので、80〜90度ほどの湯が良いでしょう。
4.フタをして数分待つ
時間は茶葉により異なります。お好みの時間でどうぞ。

5.フタで茶水を混ぜる
蓋碗を使う時はこの所作が優雅です。
利き手でフタをつまみ、傾けたまま片側を茶水に入れ、小指の方へ2度、3度動かし、茶水をやさしく混ぜます。
浮いている茶葉のくずをよけつつ茶水の濃度をならします。
両手で飲む場合はこの動作も皿ごと持って行います。
※皿ごと持った方が熱くありませんが、いずれの場合にも熱い茶器の取扱にはご注意ください。
利き手でフタをつまみ、傾けたまま片側を茶水に入れ、小指の方へ2度、3度動かし、茶水をやさしく混ぜます。
浮いている茶葉のくずをよけつつ茶水の濃度をならします。
両手で飲む場合はこの動作も皿ごと持って行います。
※皿ごと持った方が熱くありませんが、いずれの場合にも熱い茶器の取扱にはご注意ください。
6.フタの香りをかぐ。
台湾を中心に聞香杯という香りを楽しむ専用の杯がありますが、蓋碗の場合には、フタにしっかり香りが移っていますので、飲む前に香りを楽しみましょう。


7.飲む
葉がしっかり沈む茶葉の場合はフタを外して飲んでいただいても構いません。また、フタを少しずらし、フタで茶葉を抑えながら片手で飲んだり、両手で飲むこともできます。たいていの蓋碗はフタをずらした位置で安定するように作られています。
8.2度目
全部飲みきらず1/3くらいになったところで、お湯をつぎ足してください。緑茶の場合は2度か3度、烏龍茶の場合3度か4度くらいはおいしく飲むことができます。お茶は温度が高いと成分の出が早いのですが、飲んでいるうちに冷めますので、次第に出が弱くなり、湯を足した際にまた出る、というわけでこの飲み方で意外なほどおいしく飲むことができます。
●蓋碗の急須使い

烏龍茶の産地である福建省など南の方では蓋碗を急須代わりに使う飲み方も広く普及していて、安渓で茶器店を見ると、蓋碗・茶海・小杯のように急須なしの茶器セットが普通に売られています。急須使いでは普通片手で淹れますが、烏龍茶は熱湯が基本です。碗身はかなり熱くなりますので、ご注意ください。
持ち方
すきまが出来るよう蓋を少し斜めにします。それから中指と親指で碗身の最上部を持ち、蓋を人差し指で押さえて茶水を出します。そのまま茶杯に入れてもOKですが、茶海(公道杯)を使うのがベストです。茶海を使うことで茶葉が湯につかったままにならず、また、それぞれの茶杯に注ぐ前に茶水の濃度を一定にすることができます。