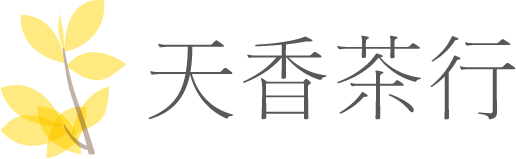豆知識 6 茶経

茶経と茶聖・陸羽
中国茶の歴史をお話しする際には、茶経に触れないわけにはいきません。
茶経は現存する世界で最も早く、非常に整った形で茶を紹介した専門書です。その内容は茶の歴史、現状、生産技術や飲み方や茶器まで幅広く、作者の陸羽(733-804)は茶聖と呼ばれています。
 紀元前に茶を初めて植えたと言われるのが茶祖・呉理真ですが、彼は後、仏教の修行を開始しその中で仏茶一家という概念を生み、甘露禅師とも呼ばれています。以降仏教と茶の関係は深く、お寺が茶の生産を促進、技術を向上させてきたという面があります。日本にお茶を伝えたのも最澄・栄西といった仏僧です。
紀元前に茶を初めて植えたと言われるのが茶祖・呉理真ですが、彼は後、仏教の修行を開始しその中で仏茶一家という概念を生み、甘露禅師とも呼ばれています。以降仏教と茶の関係は深く、お寺が茶の生産を促進、技術を向上させてきたという面があります。日本にお茶を伝えたのも最澄・栄西といった仏僧です。
さて陸羽は捨て子だったと言われており、龍蓋寺に拾われて幼少期を過ごします。ここで小さい頃から茶に親しみましたが、儒学を志し11、12歳頃になると寺を抜け出しました。その後、演劇をして暮らしたりするのですが、安史の乱を避け移住し茶の産地である浙江省へ。茶を愛する詩人や僧との交わりの中、763年、28歳の時に初稿を書き上げます。
茶経は現存する世界で最も早く、非常に整った形で茶を紹介した専門書です。その内容は茶の歴史、現状、生産技術や飲み方や茶器まで幅広く、作者の陸羽(733-804)は茶聖と呼ばれています。

蒙頂山の皇茶園。
12平方メートルに7株を呉理真が植え、
皇帝に 毎年360枚の葉が献上された
12平方メートルに7株を呉理真が植え、
皇帝に 毎年360枚の葉が献上された
さて陸羽は捨て子だったと言われており、龍蓋寺に拾われて幼少期を過ごします。ここで小さい頃から茶に親しみましたが、儒学を志し11、12歳頃になると寺を抜け出しました。その後、演劇をして暮らしたりするのですが、安史の乱を避け移住し茶の産地である浙江省へ。茶を愛する詩人や僧との交わりの中、763年、28歳の時に初稿を書き上げます。
茶経の内容
茶経は三巻十節、約7000字から成ります。概略は以下の通り。
一之源 茶の起源と樹や葉、花や根の形状、優劣など
二之具 茶の採摘、製茶などに使われる道具
三之造 茶の採摘方法、製茶の方法
四之器 24種類の茶器(茶を煮る道具、飲む茶器)の材質や構造、模様など
五之煮 茶の煮方、水質や湯の沸かし方。
六之飲 茶の飲み方
七之事 茶に関わる歴史上の事柄と効果
八之出 茶の産地と優劣
九之略 簡略化。状況が異なれば省略して良い、複雑にすれば良いというものではない
十之図 茶経の内容を図示
当時はお茶は生姜や肉桂、バター、塩などと一緒に煮るものでしたが、陸羽はよりお茶を純粋に楽しむため塩のみにし、水は山の水が良く、川の水は中、井戸水は下、山の水は鍾乳石の泉でゆるやかに流れるのが良い、あるいは、お湯は沸かしすぎるとおいしくないといったところから事細かに洗練された手順を提示しました。彼の提唱した茶のいれかたを煎茶法などど言います。事細かく説明しながら九之略で臨機応変、その通りにやらなくなっていいと言っているところが偉人ですね。
宋の時代になると点茶法と呼ばれる茶を粉状にして飲む方法が主流になりますが、後世の著作はみな茶経を前提にしており陸羽が茶の歴史において果たした役割はまさに茶聖といえるでしょう。
一之源 茶の起源と樹や葉、花や根の形状、優劣など
二之具 茶の採摘、製茶などに使われる道具
三之造 茶の採摘方法、製茶の方法
四之器 24種類の茶器(茶を煮る道具、飲む茶器)の材質や構造、模様など
五之煮 茶の煮方、水質や湯の沸かし方。
六之飲 茶の飲み方
七之事 茶に関わる歴史上の事柄と効果
八之出 茶の産地と優劣
九之略 簡略化。状況が異なれば省略して良い、複雑にすれば良いというものではない
十之図 茶経の内容を図示
当時はお茶は生姜や肉桂、バター、塩などと一緒に煮るものでしたが、陸羽はよりお茶を純粋に楽しむため塩のみにし、水は山の水が良く、川の水は中、井戸水は下、山の水は鍾乳石の泉でゆるやかに流れるのが良い、あるいは、お湯は沸かしすぎるとおいしくないといったところから事細かに洗練された手順を提示しました。彼の提唱した茶のいれかたを煎茶法などど言います。事細かく説明しながら九之略で臨機応変、その通りにやらなくなっていいと言っているところが偉人ですね。
宋の時代になると点茶法と呼ばれる茶を粉状にして飲む方法が主流になりますが、後世の著作はみな茶経を前提にしており陸羽が茶の歴史において果たした役割はまさに茶聖といえるでしょう。