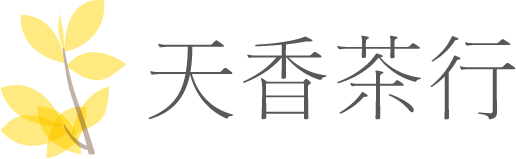歴史 3 章 2 唐代の煎茶
第3章 飲茶の歴史 寒夜客来茶当酒
<唐代の煎茶>
中国では、お茶を飲むのは喉の渇きを癒すという生理的な必要からというだけではなく、芸術でもあり、さらに文化でもあります。この芸術は唐代から始まり、その形式は「煎茶」でした。
唐代、飲まれていたのは餅茶であり、餅茶はそのまま煎じて飲むのには向いていないので、手を加えねばなりません。飲み方には、炙、碾、羅という三つの手順があります。炙は、餅茶を焙じるという意味です。餅茶は置いておくとある程度の水分を吸収するので、焙じて乾燥することで茶の香りを出やすくします。餅茶を焙じるには、風を通してはならず、燃え尽きたような火を使い灰の上で焙じるというのも良くありません。そうしないと火が揺れ動いて加熱が均一ではなくなり焙じる茶の質に影響してしまいます。焙じる際、挟みで餅茶を挟んで、できるだけ火に近づけ、始終ひっくり返します。ガマの背中のような泡が出てきたら、火から五寸ぐらい離し、弱火で焙じます。餅茶の表面が緩んだら、水蒸気がなくなるまでもとの方法で改めて焙じます。次に碾。碾(ひ)くのに使う道具は、碾(堕という台を含む)と「拂塵(馬の尾などを束ねて柄の先につけ塵を払うもの)」です。茶碾は、唐代は一般的に木製です。しかし、宋代の蔡襄の『茶録』と宋の徽宗の『大観茶論』には、「碾以銀為上,熟鉄次之」という記載があり、銀や熟鉄で茶碾を作るのが良いと言います。碾ですりつぶした茶末は、さらに羅という手順が必要で、茶末が大きすぎないようにします。羅とは篩のことです。底は竹の節で作られ、口径は12センチ程しかなく、上は紗や絹で覆っています。この紗や絹の穴がどれほどの大きさか、現在は知ることができません。陸羽の『茶経』の「末之上者,其屑如細米(上等の茶末は細かい米に似ている)」「碧粉縹塵,非末也(緑の細かい塵のようであれば良い茶末ではない)」などの記載から見れば、高級な茶末は、かけらというほど大きくはなく、粉末でもありません、細かい顆粒だと推測できます。すりつぶされ、また、篩にかけられた茶末は、色や光沢が黄金のようで、細かくきれいに揃っているので、詩人たちも詩に詠んでいます。唐代の詩人・李群玉は、『龍山人恵石廩方及団茶』の詩で、「碾成黄金粉,軽嫩如松花(碾いて黄金の粉にすると軽やかで若々しい様子は松の花のようだ)」という詩句でその美しさを称えました。
末茶を焙じ終えたら、茶を煎じます。煎茶には、湯を沸かしお茶を煮るという二つの手順があります。まずは、水を鍑(口が大きく、両側に四角い柄がある鍋で陸羽が設計した茶具)に注いで、水が沸騰するまで加熱します。「沸如魚目,微有声(魚目ほどの泡が生じ、少し音がある)」のが第一の沸騰、この時、適量の塩を入れ味を整えます。「縁辺如湧泉連珠(鍋の縁に泡が絶え間なく湧出る)」のが第二の沸騰。この時、お湯をひとすくい汲出し、竹挟みで鍑の中をかき混ぜ、渦を作って沸騰の程度を均します。それから、「則」という茶を測る小さい杓で一則の茶末を量って渦の中心に入れ、また、かき混ぜます。茶湯が「勢如奔騰濺沫(十分沸騰し、しぶきが四方に飛び散る)」のが第三の沸騰。前に汲み出したひとすくいの水を鍑に戻し、お湯の沸騰を中止させます。この時に、沫餑、いいかえると、茶湯の上に浮かんだあぶく、湯花が現れます。古代の人々は、沫餑の多いほうが優れたものだと認識していました。『茶経』は、お茶の湯花を沫、餑、花の三種類に分け、「華の薄いものを沫、厚いものを餑、細かく軽いものを花という。花は棗の花のように円い池の上に浮かび、また曲がりくねった淵と突き出た小島の間に新たに育った青々とした浮き草のようでもあり、晴れわたる天空に浮かぶうろこ雲のようでもある。沫は水のみぎわの緑に似て、あるいは器に撒いた菊の花びらのようである。 餑は茶が沈み淀んでいる時、水がひとたび沸騰すると多くの泡が水面に重なり集まる、純白の積もった雪のようである。」と言っています。湯花が上に浮かぶのを待ち、お茶の香りも揮発した丁度良い頃合いで「酌茶」を始めます。
酌茶とは、杓でお茶を茶盞に分けることです。酌茶の基本的な技は、各茶碗の沫餑を等しくすることです。沫餑は、茶湯のエッセンスであり、等しくしないと茶湯の味わいも異なります。茶湯と湯花を各茶盞に均等に分けると、それぞれの茶盞の中に、黄色味を帯びた若々しい緑の茶湯には、積もった雪のような湯花が同じように浮かび、お互いに引き立て合い非常に趣があり、見た人の目や心を楽しませます。唐代の詩人は、よくこの様子を詩に詠んでいます。曹鄴は『故人寄茶』において「碧沉霞脚砕,香泛乳花軽,六腑睡神去,数朝詩思清代(細かな茶葉の緑は霞のように底に沈み、香りが浮かび乳白の湯花が軽やかで、六腑に潜む睡魔が去り、数日はすっきりと詩意が生まれる)」と詠み、刘禹錫は『西山蘭若試茶歌』で「白雲満碗花徘徊,悠揚噴鼻宿醒散(白い雲が碗に満ち花が歩き回るようで香りは悠揚と漂い頭がすっきりとする)」としています。このように芳醇で爽やかな味わい、後味も尽きないお茶を飲むと、頭がすっきりとするだけでなく、ひらめきも刺激して、詩歌を作る気持ちを引き起こします。文人墨客が「一日もお茶が欠かせない」というのも道理でしょう。
酌茶の数量にも陸羽は一定のきまりを設けました。茶を煎じるとき適当に水を注ぐのには反対で、茶湯を煎じ終えたら、「珍鮮馥烈者,其碗数三,次之者,碗数五」が良いといいます。つまり、一則の茶末で一升の茶湯を煎じ、味を濃く強くしたければ、三つの茶盞に分け、それに次ぐ濃さであれば五つの茶盞に分けます。エッセンスが蒸気とともになくならないよう、熱いうちに飲み終えます。残りは沫餑を全部分け終えているので、ほとんど味がなく、喉の乾きを癒すのではなければ飲む必要はありません。もし、人数が四人や六人に増え、一碗足りない場合は「隽永(予め残しおいた茶湯)」で補充します。
茶湯をうまく煮るには燃料選びもとても重要で、陸羽は、一番良いのは木炭、次は硬い薪を使うのが良いと考えていました。生臭い匂いがついた薪、あるいは油の多いもの、朽ちた木の類いは適していません。木炭で燃やした火を「活火」と呼びます。唐代の人々はこの活火を重視し、詩人の李約も唐代の温庭筠の『採茶録』から引用して次のように言っています。「茶は弱火で焙じ活火で煎じるのが良い。活火とは炭火のうち炎があるものをいう。茶湯はみだりに沸騰させないことで茶の良さを引き出せる。はじめ、魚の目ほどの泡が生じ、少し音がある、半ばには鍋の縁に泡が絶え間なく湧き出で連なり、最後は十分沸騰し水面が波打つ、湯気が消えるとこれを老湯と呼ぶ。この三沸の方法は、活火でしかできない」
この外、茶湯の品質は水質とさらに深い関係があります。
唐代の煎茶法は、煎じるにも飲むにも細やかで、お茶を飲むのは喉の乾きを癒すことから、芸術を楽しむことへと昇華しています。一つひとつの煩瑣な手順の後でこそ軽やかに啜りゆっくりと味わう楽しみがあり、世上を忘れ、こだわりなく、静謐で、陶然とした愉悦の境地に酔い、物質と精神の二重の満足感へたどり着きます。このため、煎茶法は、陸羽が創造してから唐代を通じて流行し衰えることがなかったのです。
唐代、飲まれていたのは餅茶であり、餅茶はそのまま煎じて飲むのには向いていないので、手を加えねばなりません。飲み方には、炙、碾、羅という三つの手順があります。炙は、餅茶を焙じるという意味です。餅茶は置いておくとある程度の水分を吸収するので、焙じて乾燥することで茶の香りを出やすくします。餅茶を焙じるには、風を通してはならず、燃え尽きたような火を使い灰の上で焙じるというのも良くありません。そうしないと火が揺れ動いて加熱が均一ではなくなり焙じる茶の質に影響してしまいます。焙じる際、挟みで餅茶を挟んで、できるだけ火に近づけ、始終ひっくり返します。ガマの背中のような泡が出てきたら、火から五寸ぐらい離し、弱火で焙じます。餅茶の表面が緩んだら、水蒸気がなくなるまでもとの方法で改めて焙じます。次に碾。碾(ひ)くのに使う道具は、碾(堕という台を含む)と「拂塵(馬の尾などを束ねて柄の先につけ塵を払うもの)」です。茶碾は、唐代は一般的に木製です。しかし、宋代の蔡襄の『茶録』と宋の徽宗の『大観茶論』には、「碾以銀為上,熟鉄次之」という記載があり、銀や熟鉄で茶碾を作るのが良いと言います。碾ですりつぶした茶末は、さらに羅という手順が必要で、茶末が大きすぎないようにします。羅とは篩のことです。底は竹の節で作られ、口径は12センチ程しかなく、上は紗や絹で覆っています。この紗や絹の穴がどれほどの大きさか、現在は知ることができません。陸羽の『茶経』の「末之上者,其屑如細米(上等の茶末は細かい米に似ている)」「碧粉縹塵,非末也(緑の細かい塵のようであれば良い茶末ではない)」などの記載から見れば、高級な茶末は、かけらというほど大きくはなく、粉末でもありません、細かい顆粒だと推測できます。すりつぶされ、また、篩にかけられた茶末は、色や光沢が黄金のようで、細かくきれいに揃っているので、詩人たちも詩に詠んでいます。唐代の詩人・李群玉は、『龍山人恵石廩方及団茶』の詩で、「碾成黄金粉,軽嫩如松花(碾いて黄金の粉にすると軽やかで若々しい様子は松の花のようだ)」という詩句でその美しさを称えました。
末茶を焙じ終えたら、茶を煎じます。煎茶には、湯を沸かしお茶を煮るという二つの手順があります。まずは、水を鍑(口が大きく、両側に四角い柄がある鍋で陸羽が設計した茶具)に注いで、水が沸騰するまで加熱します。「沸如魚目,微有声(魚目ほどの泡が生じ、少し音がある)」のが第一の沸騰、この時、適量の塩を入れ味を整えます。「縁辺如湧泉連珠(鍋の縁に泡が絶え間なく湧出る)」のが第二の沸騰。この時、お湯をひとすくい汲出し、竹挟みで鍑の中をかき混ぜ、渦を作って沸騰の程度を均します。それから、「則」という茶を測る小さい杓で一則の茶末を量って渦の中心に入れ、また、かき混ぜます。茶湯が「勢如奔騰濺沫(十分沸騰し、しぶきが四方に飛び散る)」のが第三の沸騰。前に汲み出したひとすくいの水を鍑に戻し、お湯の沸騰を中止させます。この時に、沫餑、いいかえると、茶湯の上に浮かんだあぶく、湯花が現れます。古代の人々は、沫餑の多いほうが優れたものだと認識していました。『茶経』は、お茶の湯花を沫、餑、花の三種類に分け、「華の薄いものを沫、厚いものを餑、細かく軽いものを花という。花は棗の花のように円い池の上に浮かび、また曲がりくねった淵と突き出た小島の間に新たに育った青々とした浮き草のようでもあり、晴れわたる天空に浮かぶうろこ雲のようでもある。沫は水のみぎわの緑に似て、あるいは器に撒いた菊の花びらのようである。 餑は茶が沈み淀んでいる時、水がひとたび沸騰すると多くの泡が水面に重なり集まる、純白の積もった雪のようである。」と言っています。湯花が上に浮かぶのを待ち、お茶の香りも揮発した丁度良い頃合いで「酌茶」を始めます。
酌茶とは、杓でお茶を茶盞に分けることです。酌茶の基本的な技は、各茶碗の沫餑を等しくすることです。沫餑は、茶湯のエッセンスであり、等しくしないと茶湯の味わいも異なります。茶湯と湯花を各茶盞に均等に分けると、それぞれの茶盞の中に、黄色味を帯びた若々しい緑の茶湯には、積もった雪のような湯花が同じように浮かび、お互いに引き立て合い非常に趣があり、見た人の目や心を楽しませます。唐代の詩人は、よくこの様子を詩に詠んでいます。曹鄴は『故人寄茶』において「碧沉霞脚砕,香泛乳花軽,六腑睡神去,数朝詩思清代(細かな茶葉の緑は霞のように底に沈み、香りが浮かび乳白の湯花が軽やかで、六腑に潜む睡魔が去り、数日はすっきりと詩意が生まれる)」と詠み、刘禹錫は『西山蘭若試茶歌』で「白雲満碗花徘徊,悠揚噴鼻宿醒散(白い雲が碗に満ち花が歩き回るようで香りは悠揚と漂い頭がすっきりとする)」としています。このように芳醇で爽やかな味わい、後味も尽きないお茶を飲むと、頭がすっきりとするだけでなく、ひらめきも刺激して、詩歌を作る気持ちを引き起こします。文人墨客が「一日もお茶が欠かせない」というのも道理でしょう。
酌茶の数量にも陸羽は一定のきまりを設けました。茶を煎じるとき適当に水を注ぐのには反対で、茶湯を煎じ終えたら、「珍鮮馥烈者,其碗数三,次之者,碗数五」が良いといいます。つまり、一則の茶末で一升の茶湯を煎じ、味を濃く強くしたければ、三つの茶盞に分け、それに次ぐ濃さであれば五つの茶盞に分けます。エッセンスが蒸気とともになくならないよう、熱いうちに飲み終えます。残りは沫餑を全部分け終えているので、ほとんど味がなく、喉の乾きを癒すのではなければ飲む必要はありません。もし、人数が四人や六人に増え、一碗足りない場合は「隽永(予め残しおいた茶湯)」で補充します。
茶湯をうまく煮るには燃料選びもとても重要で、陸羽は、一番良いのは木炭、次は硬い薪を使うのが良いと考えていました。生臭い匂いがついた薪、あるいは油の多いもの、朽ちた木の類いは適していません。木炭で燃やした火を「活火」と呼びます。唐代の人々はこの活火を重視し、詩人の李約も唐代の温庭筠の『採茶録』から引用して次のように言っています。「茶は弱火で焙じ活火で煎じるのが良い。活火とは炭火のうち炎があるものをいう。茶湯はみだりに沸騰させないことで茶の良さを引き出せる。はじめ、魚の目ほどの泡が生じ、少し音がある、半ばには鍋の縁に泡が絶え間なく湧き出で連なり、最後は十分沸騰し水面が波打つ、湯気が消えるとこれを老湯と呼ぶ。この三沸の方法は、活火でしかできない」
この外、茶湯の品質は水質とさらに深い関係があります。
唐代の煎茶法は、煎じるにも飲むにも細やかで、お茶を飲むのは喉の乾きを癒すことから、芸術を楽しむことへと昇華しています。一つひとつの煩瑣な手順の後でこそ軽やかに啜りゆっくりと味わう楽しみがあり、世上を忘れ、こだわりなく、静謐で、陶然とした愉悦の境地に酔い、物質と精神の二重の満足感へたどり着きます。このため、煎茶法は、陸羽が創造してから唐代を通じて流行し衰えることがなかったのです。