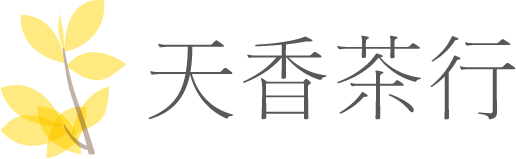歴史 3 章 飲茶の歴史 1 春秋時代の生煮羹飲
第3章 飲茶の歴史 寒夜客来茶当酒
中国では、お茶を飲むという行為も、中国人に一貫した偏らず、過ぎず及ばず、何事も中庸にかなうという哲学思想と生活様式に強く影響され、わざとらしさのないものとなっています。
中国人がお茶を飲む際、最もこだわるのは風情です。「歌停曲終」「停鼓看書」「夜深共語」「小橋書船」「茂林修竹」「酒閘人散」といった言葉は、すべてお茶を楽しむのに良い環境やタイミングを表しています。
「寒夜客来茶当酒(寒い夜に客が来て茶を酒の代わりにする)」という言葉は、客人と主人の間の調和した楽しい雰囲気を表しているだけではなく、雅な趣も含んでいます。
お茶を飲むのには、もう数千年の歴史があり、製茶技術の発展と茶葉の種類が増えるのに伴い、各時代の飲み方も様々です。王朝の変遷に沿って史料を見てみましょう。
古代の中国人は、野生の茶樹を発見し、新鮮な茶葉を咀嚼することから、お茶を利用し始めました。伝説上、初めて茶樹の新鮮な葉を味わい、茶葉の不思議な解毒効用を見つけた人は、神農氏であると言われています。神農氏の名を借りて作られた漢代の薬書『神農本草経』には、こういう記載があります。「神農嘗百草之滋味,水泉之甘苦,令民知所避就,当此之時,日遇七十二毒,得茶而解」。神農氏とは、いつの時代の人でしょうか。『荘子・盗跖篇』の「神農之氏….只知其母,不知其父」という記載を見れば、母はわかるが父はわからない母系氏族社会に暮らしていたことがわかります。ここから考えると、お茶の発見と利用は、現在までに約一万年の時間を経ていると推測されます。
古代の人が最初に茶葉を利用したのは生のまま咀嚼して食べるという形で、後に、火で煮て羹にして飲むようになりますが、これは現在の野菜スープを煮るのに似ています。お茶の利用の最初の段階では、製茶などは全くなく、羹にして飲み、茶葉を料理して食べていました。『晏子春秋』という春秋時代、斉の景公の時代の宰相である晏嬰の一生の業績を記した史書には、茶葉を野菜として食べたという記載があります。「晏相斉景公時,食脱粟之飯,炙三弋五卵,茗菜而已。」晏嬰は国の宰相でありながら、飲食は質素で、玄米のご飯といくつの肉類の料理以外、茗(茶)菜しかないという意味です。晏嬰が食べていた茗菜は、日に当て乾燥したりしていない新鮮な茶葉です。こういう茶葉を野菜として食べる習慣は、現在でも、一部のところには残っています。例えば、雲南省の基諾族には、今に至るまで、「凉拌茶」というものを食べる習慣があります。「凉拌茶」とは、採取した新鮮な茶葉を揉んで細かくしてから碗に入れ、にんにく、唐辛子、塩などを少し入れ、泉の水を加え、混ぜてならし、美味しく料理したものです。
中国人がお茶を飲む際、最もこだわるのは風情です。「歌停曲終」「停鼓看書」「夜深共語」「小橋書船」「茂林修竹」「酒閘人散」といった言葉は、すべてお茶を楽しむのに良い環境やタイミングを表しています。
「寒夜客来茶当酒(寒い夜に客が来て茶を酒の代わりにする)」という言葉は、客人と主人の間の調和した楽しい雰囲気を表しているだけではなく、雅な趣も含んでいます。
お茶を飲むのには、もう数千年の歴史があり、製茶技術の発展と茶葉の種類が増えるのに伴い、各時代の飲み方も様々です。王朝の変遷に沿って史料を見てみましょう。
古代の中国人は、野生の茶樹を発見し、新鮮な茶葉を咀嚼することから、お茶を利用し始めました。伝説上、初めて茶樹の新鮮な葉を味わい、茶葉の不思議な解毒効用を見つけた人は、神農氏であると言われています。神農氏の名を借りて作られた漢代の薬書『神農本草経』には、こういう記載があります。「神農嘗百草之滋味,水泉之甘苦,令民知所避就,当此之時,日遇七十二毒,得茶而解」。神農氏とは、いつの時代の人でしょうか。『荘子・盗跖篇』の「神農之氏….只知其母,不知其父」という記載を見れば、母はわかるが父はわからない母系氏族社会に暮らしていたことがわかります。ここから考えると、お茶の発見と利用は、現在までに約一万年の時間を経ていると推測されます。
古代の人が最初に茶葉を利用したのは生のまま咀嚼して食べるという形で、後に、火で煮て羹にして飲むようになりますが、これは現在の野菜スープを煮るのに似ています。お茶の利用の最初の段階では、製茶などは全くなく、羹にして飲み、茶葉を料理して食べていました。『晏子春秋』という春秋時代、斉の景公の時代の宰相である晏嬰の一生の業績を記した史書には、茶葉を野菜として食べたという記載があります。「晏相斉景公時,食脱粟之飯,炙三弋五卵,茗菜而已。」晏嬰は国の宰相でありながら、飲食は質素で、玄米のご飯といくつの肉類の料理以外、茗(茶)菜しかないという意味です。晏嬰が食べていた茗菜は、日に当て乾燥したりしていない新鮮な茶葉です。こういう茶葉を野菜として食べる習慣は、現在でも、一部のところには残っています。例えば、雲南省の基諾族には、今に至るまで、「凉拌茶」というものを食べる習慣があります。「凉拌茶」とは、採取した新鮮な茶葉を揉んで細かくしてから碗に入れ、にんにく、唐辛子、塩などを少し入れ、泉の水を加え、混ぜてならし、美味しく料理したものです。
<春秋時代の生煮羹飲(生の葉を煮て羹にして飲む)>
周代と春秋時代に至り、古代の人々は、供えものにするため茶葉を長く保管できるように、日光にあてて乾燥し、随時用いるという方法を身につけます。このように茶葉を日にあてて乾燥し、煮て羹にする飲み方は長い間続きました。晋代の人・郭璞は『爾雅』という古代の字典に注釈した際、茶葉は「可煮作羹飲(煮て羹にし飲める)」と言っています。晋代の人々はこの飲み方を採用していたのです。
現在、中国の西南地区、湖南と湖北、広東と広西の少数民族には、古代から残されたお茶を食べる習慣があります。例えば、雲南省西部の徳広傣族や景頗族自治州の瑞麗県の濮族支系である徳昂族の人々は、しばしば「水茶」を食べます。これはいわゆる「塩で漬け込んだ茶葉」で、新鮮な茶葉が萎びるまで日光に当て、小篭に入れ、塩を撒き、数日のうち篭から取り出し噛んで食べ、噛んだ後、屑は吐き出します。こういう食べ方は、喉の渇きを癒すばかりではなく、病気を治す効用もあると言われます。
史料によると、中国の西南地区では、2000年以上前からお茶を生産していました。秦もしくは、漢代に本となった『爾雅・釈木篇』には、「檟,苦茶也 (檟とは、苦いお茶である)」という記載があります。清代の学者顧炎武は『日知録』において「自秦人取蜀之后,始有茗飲之事(秦の人が蜀を征服した後、お茶を飲み始めた)」と考証しています。
現在、中国の西南地区、湖南と湖北、広東と広西の少数民族には、古代から残されたお茶を食べる習慣があります。例えば、雲南省西部の徳広傣族や景頗族自治州の瑞麗県の濮族支系である徳昂族の人々は、しばしば「水茶」を食べます。これはいわゆる「塩で漬け込んだ茶葉」で、新鮮な茶葉が萎びるまで日光に当て、小篭に入れ、塩を撒き、数日のうち篭から取り出し噛んで食べ、噛んだ後、屑は吐き出します。こういう食べ方は、喉の渇きを癒すばかりではなく、病気を治す効用もあると言われます。
史料によると、中国の西南地区では、2000年以上前からお茶を生産していました。秦もしくは、漢代に本となった『爾雅・釈木篇』には、「檟,苦茶也 (檟とは、苦いお茶である)」という記載があります。清代の学者顧炎武は『日知録』において「自秦人取蜀之后,始有茗飲之事(秦の人が蜀を征服した後、お茶を飲み始めた)」と考証しています。