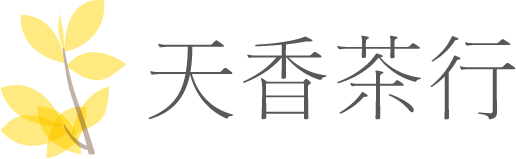Collections
-

茶壺・急須・ティーポット
急須・ティーポットは言わずと知れた茶を淹れる定番の茶器。中国では茶壺(ちゃふう)と呼ばれます。耐熱ガラスポットや紫砂壺など実用はもちろん芸術品としても発展、見ているだけでも趣きがある茶器です。
-

茶葉バッグ茶器混合セット
茶葉やティーバッグと茶器を合わせたセット商品。手にしたその時からお湯があればお使いいただけます。日本では馴染みのない品が多いので、贈り物としても楽しい品揃えです。